「競合と同じような求人情報では、自社の魅力が伝わりきらない…」
「採用面談で、候補者との間に認識のズレを感じることが多い…」
企業の採用担当者として、このような課題を感じていませんか?
テキストと写真だけでは伝えきれない、企業の「リアルな魅力」を届け、候補者とのミスマッチを減らす強力な一手として、「採用動画」がますます重要になっています。
この記事では、単に成功事例を羅列するだけではありません。企業の採用課題を解決し、役員会での承認を得られるような企画のヒントとなるよう、「なぜその動画が成功したのか」という戦略的な視点から、目的別の成功事例と、明日から使える実践的なノウハウを徹底的に解説します。
なぜ今、採用動画が重要なのか?- 成功の背景にある3つの戦略的理由
採用活動において動画の活用が急速に広がっていますが、その背景には明確な戦略的理由が存在します。なぜ今、多くの企業が採用動画に投資するのでしょうか。
それは、現代の採用市場が抱える課題に対する、動画ならではの強力な解決力にあります。ここでは、採用動画の重要性を裏付ける3つの理由を解説します。
理由1:テキスト情報の飽和と「情報のリッチ化」への対応
現代の候補者は、日常的にスマートフォンでYouTubeやSNSの動画コンテンツに触れており、情報を動画で得ることに慣れ親しんでいます。求人サイトや企業の採用ページに溢れるテキスト情報を一つひとつ熟読する候補者は、もはや少数派かもしれません。
動画は、テキストの数千倍とも言われる圧倒的な情報量を持ち、わずか1分程度の短い時間で、働く社員の表情や声のトーン、オフィスの雰囲気といった「非言語情報」まで伝えることができます。
テキストだけでは伝えきれない企業の「熱量」や「カルチャー」をリッチな情報として届けることで、数多ある競合の中から候補者の記憶に残り、興味を惹きつけることが可能になるのです。
理由2:候補者の「知りたい」に応える透明性の担保
候補者が企業選びで重視する点は、給与や福利厚生といった条件だけではありません。「実際にどのような人たちが、どのような環境で、どのように働いているのか」という、リアルな情報をますます求めるようになっています。
この「知りたい」という欲求に対し、最も効果的に応えられるのが動画です。
編集されていない、ありのままのオフィス風景や、社員同士の自然な会話は、作り込まれた文章よりもはるかに高い信頼性を持ちます。企業のポジティブな側面だけでなく、課題やそれを乗り越えようとする姿勢まで正直に見せることで、候補者は入社後の働き方を具体的にイメージでき、企業への信頼感を深めることができます。
この透明性の担保が、候補者の意思決定を強力に後押しします。
理由3:採用におけるミスマッチの低減とエンゲージメントの向上
「入社前に抱いていたイメージと違った」という理由での早期離職は、企業にとっても採用した社員にとっても大きな損失です。採用動画は、この深刻なミスマッチを未然に防ぐための強力なツールとなります。
動画を通じて仕事のやりがいだけでなく、厳しさや大変な側面も含めたリアルな姿を事前に伝えることで、候補者の過度な期待を調整し、適切な「期待値コントロール」が可能になります。
- 入社前: 企業のリアルな姿を理解し、納得した上で入社を決意する。
- 入社後: 入社前後のギャップが少ないため、スムーズに業務に馴染み、早期に活躍(エンゲージメント向上)できる。
結果として、採用動画への投資は、採用コストの削減や入社後の定着率向上といった、経営的なメリットにも直結するのです。
【目的別】採用動画の成功事例 – 戦略とクリエイティブを徹底解剖
ここからは、具体的な採用動画の成功事例を、採用担当者が抱える課題(目的)別に分類してご紹介します。
ただ「かっこいい」「面白い」で終わらせず、「なぜこの動画は候補者の心を動かしたのか」という戦略的な視点で分析します。各事例から、自社の採用課題を解決するためのヒントを見つけ出してください。
Part 1:企業の「認知度・ブランドイメージ」を向上させるための事例
まずは多くの候補者に会社を知ってもらい、「なんだか面白そうな会社だな」「ここで働いてみたい」というポジティブな第一印象を植え付けることを目的とした事例です。
潤沢な予算を活かして企業のブランドイメージを映像美やストーリーテリングで表現する動画が多く見られます。
Part 2:「企業文化・働く人」の魅力を伝え、カルチャーフィットを促す事例
給与や待遇といった条件面だけではなく、「この人たちと一緒に働きたい」と候補者に感じてもらい、入社後のカルチャーフィットを重視する目的の動画事例です。
定番のインタビュー動画でも、一工夫加えることで社員の本音やリアルな人柄を引き出すことができます。
事例を真似るだけでは失敗する – 採用動画を成功に導く3つのステップ
多くの成功事例を見てきましたが、注意すべきは、これらのクリエイティブを表面的な「面白い」「かっこいい」という理由だけで真似てしまうことです。
成功事例の裏側には、必ずしっかりとした戦略的プロセスが存在します。ここからは、採用動画を成功に導くために不可欠な3つのステップを、具体的なアクションと共に解説します。
Step 1:「誰に、何を伝え、どうなってほしいか」目的とKPIを明確にする
動画制作に取り掛かる前に、最も時間をかけて考えるべきなのが、この「目的の明確化」です。ここが曖昧なままでは、どれだけクオリティの高い映像を作っても、採用成果には繋がりません。
| 考えるべき項目 |
具体的な問いかけ |
| ターゲット(誰に) |
新卒? 中途? エンジニア? 営業? 会社のことを全く知らない層? |
| コアメッセージ(何を) |
最も伝えたい自社の魅力は何か?(例: 挑戦できる風土、社会貢献性、技術力の高さ) |
| ゴール(どうなってほしいか) |
この動画を見た候補者に、どのような気持ちになり、何をしてほしいか?(例: 共感してエントリーしてほしい) |
| KPI(目標達成の指標) |
ゴールの達成度を何で測るか?(例: 動画経由の応募数、説明会参加率、内定承諾率) |
これらの項目を事前にチームで議論し、言語化することで、制作の方向性がブレることを防ぎます。
Step 2:目的に合わせた最適な動画タイプと表現方法を選択する
Step1で定めた目的によって、制作すべき動画のタイプは大きく変わります。
例えば、「とにかく会社の認知度を上げたい」という目的であればインパクトのあるブランディング動画が有効ですが、「カルチャーフィットする人材が欲しい」のであれば、社員のリアルな姿を見せるインタビュー動画の方が適しています。
| 目的(採用課題) |
有効な動画タイプ |
| 認知度・ブランドイメージ向上 |
ブランディング動画、コンセプトムービー |
| 企業文化・働く人の魅力訴求 |
社員インタビュー、オフィスツアー、Vlog、座談会 |
| 事業内容・仕事のやりがい理解 |
事業紹介動画、プロジェクトストーリー、技術解説動画 |
目的と手段を正しく結びつけることが、効果的な動画制作の鍵です。
Step 3:制作して終わりではない。「届ける」ための活用戦略を立てる
素晴らしい動画が完成しても、ターゲットとする候補者に見てもらえなければ意味がありません。動画を「どこで」「どのように」見てもらうのか、という活用戦略を制作段階から計画しておくことが重要です。
- 自社採用サイト: 企業の魅力を深く伝える中心的な場所。少し長めの動画(3〜5分)も配置可能。
- SNS (YouTube, X, TikTok): 認知度向上が目的。短尺(1分以内)でインパクトのある動画が効果的。
- Web説明会: 冒頭で動画を流すことで、候補者の心を掴み、企業理解を深める。
- スカウトメール: 文面に動画URLを記載し、テキストだけでは伝わらない魅力を補完する。
各プラットフォームの特性を理解し、動画を最適化して展開することで、その効果を最大化することができます。
採用動画に関する「よくある質問」- 予算、制作、期間の不安を解消
最後に、採用担当者の皆様が動画制作を具体的に進める上で抱えるであろう、現実的な疑問にお答えします。特に気になる予算や制作体制、動画の長さについての不安をここで解消しましょう。
Q1. 費用はどれくらいかかる?予算別の制作イメージ
採用動画の費用は、企画内容やクオリティによって大きく変動します。一概には言えませんが、予算別に「できること」の目安を以下に示します。
| 予算帯 |
できることのイメージ |
| 〜30万円 |
スマートフォンでの撮影や簡易的な編集が中心。社員インタビューや簡単なオフィス紹介など、内製に近い形での制作。 |
| 30万円〜100万円 |
プロの撮影クルー(カメラマン、音声など)を手配可能。企画・構成のサポートを受けられ、一定のクオリティが担保される。 |
| 100万円以上 |
企画・構成からキャスティング、撮影、編集まで一貫して依頼可能。アニメーションやCG、ドローン撮影など、高度な演出も選択肢に入る。 |
まずは自社の目的と照らし合わせ、どのレベルのクオリティを目指すかを検討することが重要です。
Q2. 内製(自社制作)と外注(制作会社)はどちらが良い?
内製と外注には、それぞれメリット・デメリットがあります。どちらが良いかは、企業の状況や動画制作の目的によって異なります。
| |
メリット |
デメリット |
| 内製(自社制作) |
・コストを抑えられる
・スケジュール調整が容易
・企業のリアルな雰囲気を伝えやすい |
・クオリティの担保が難しい
・担当者の負担が大きい
・企画や編集のノウハウが必要 |
| 外注(制作会社) |
・高いクオリティが期待できる
・客観的な視点での企画提案
・最新のトレンドを反映できる |
・コストがかかる
・コミュニケーションコストが発生する
・会社の深い理解を伝えるのが難しい場合も |
「まずは低コストで試したい」「社員のリアルさを最優先したい」という場合は内製から始めてみるのが良いでしょう。
一方で、「企業のブランドイメージを大きく向上させたい」「専門的な演出を取り入れたい」という場合は、プロである制作会社への外注がおすすめです。
Q3. 動画の最適な長さは?
動画の最適な長さは、「一概に〇分が良い」という正解はありません。重要なのは、動画を掲載する「媒体」と、視聴する「候補者の状況」に合わせることです。
- SNS (TikTok, Instagramリールなど): 15秒〜1分。認知度向上が目的。短時間でインパクトを残すことが最優先。
- 採用サイトやYouTubeチャンネル: 3分〜5分。企業への興味が既にある候補者向け。事業内容や企業文化をじっくり伝える。
- 会社説明会: 5分〜10分。参加者を惹きつけるためのコンテンツ。ストーリー性のある長尺動画も有効。
各プラットフォームの特性を理解し、動画を最適化して展開することで、その効果を最大化することができます。
まとめ:明日から始める、採用動画制作の第一歩
この記事では、採用動画の戦略的な重要性から、目的別の成功事例、そして制作を成功させるための具体的なステップまでを解説してきました。
重要なのは、単に流行りの動画を真似るのではなく、自社の採用課題と真摯に向き合い、その解決策として動画を戦略的に活用するという視点です。
この記事を読んで、採用動画の可能性を感じていただけたなら、ぜひ次の一歩を踏み出してみてください。
あなたの会社にしか伝えられない魅力が、必ずあります。採用動画という翼を得て、その魅力を未来の仲間に届ける旅を、今日から始めてみませんか。







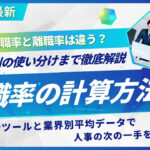

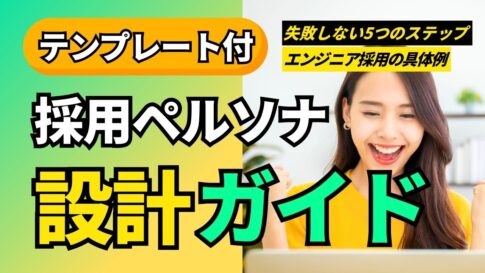


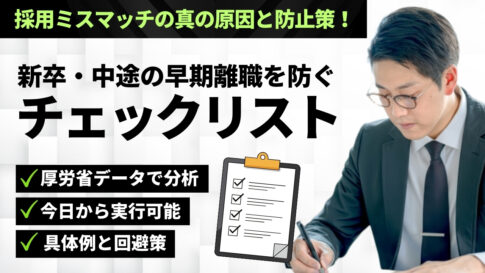

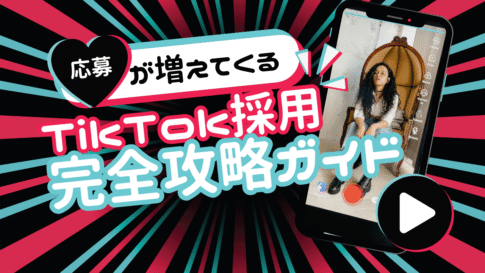

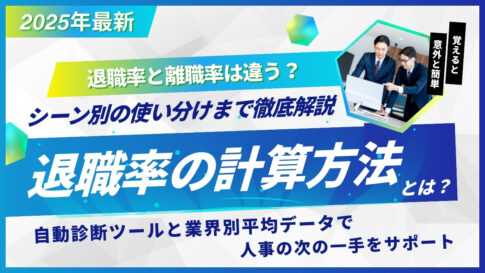



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。