
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「予算がない」は言い訳にならない。採用ショート動画は、知恵と工夫で今すぐ始められる

予算がないからと諦める前に、まず知恵と工夫で始めてみることが大切です。
「最近の若い世代はSNSで就職先を探すらしいね。うちも何かイマドキな採用、やってみたら?まあ、予算はないんだけど…」
経営会議で、社長からこんな言葉を投げかけられて、頭を抱えていませんか。Webで「採用動画 制作」と検索すれば、表示されるのは立派な制作会社ばかり。きらびやかな実績の数々と、その横に表示される「お見積もりはこちら」のボタンを見て、そっとブラウザを閉じた経験があるかもしれません。
ご安心ください。この記事は、かつてのあなたと同じように、限られた予算と情報の中で、新しい採用の形を模索するすべての人事・採用担当者のために書きました。
この記事を最後まで読めば、高価な撮影機材や専門知識、そして外注費用がなくても、明日からあなたの会社で採用ショート動画を始めるための、具体的で実践的な方法がすべてわかります。
単なる事例紹介だけではありません。なぜその動画が成功したのかという「分析」、予算ゼロから始めるための「内製化ロードマップ」、そして、すぐに使える「企画テンプレート」まで、私たちが持つノウハウのすべてを詰め込みました。
さあ、一緒に新しい採用の扉を開きましょう。
そもそも、なぜZ世代の採用にショート動画が効くのか?3つの理由

なぜショート動画が今の若い世代に響くんでしょうか。

良い質問ですね。単なる流行ではなく、現代の就職活動における必然なんです。
「なぜ、わざわざショート動画なの?」と感じる方もいるかもしれません。この施策の必要性を、上司や経営層に説明するための論理的な根拠を3つのポイントに整理しました。これは単なる流行ではなく、現代の就職活動における必然なのです。
1. 可処分時間ならぬ「可処分精神」を奪い合う時代の最適解だから

情報過多の時代、求職者の集中力は限られています。短時間で核心を伝えることが重要です。
現代は、情報の洪水です。私たちは、1日の中で使える「時間」だけでなく、何かに集中するための「精神力」までも、常に様々なコンテンツに奪い合われています。分厚い採用パンフレットや、長時間の説明会動画を、最後までじっくりと見てくれる候補者はどれだけいるでしょうか。
その点、ショート動画は、わずか15秒から1分という短時間で、企業の核心的な魅力やメッセージを直感的に伝えることができます。
隙間時間で気軽に見ることができ、候補者の貴重な「可処分精神」を無駄にしません。情報過多の時代において、最も効率的にメッセージを届けられるフォーマットなのです。
2. 加工されていない「リアル」な情報しか信用しないから

完璧すぎる映像より、現場の生の声の方が信頼されるんです。
デジタルネイティブであるZ世代は、幼い頃からインターネット上の無数の情報に触れてきました。その結果、企業が発信する美しく作り込まれた広告や宣伝文句に対して、一歩引いて見るという鋭い感性を持っています。彼らが本当に知りたいのは、加工された情報ではなく、その裏側にある「本物」の姿です。
プロが作った完璧すぎる映像よりも、社員がスマートフォンで撮影した少しラフな動画の方が、かえって「リアル」で信頼できる情報として受け取られます。社員の自然な笑顔、ありのままのオフィスの様子、飾らない言葉。そうした情報こそが、彼らの心を動かすのです。
3. 企業の「中の人」との偶発的な出会いを求めているから

最近は偶然の出会いから企業を知ることも多いですよね。
従来の就職活動は、学生が企業の名前を「検索」することから始まるのが一般的でした。しかし、SNSが生活の一部となった今、「偶然の出会い(ディスカバリー)」から企業に興味を持つケースが急増しています。
TikTokやInstagramのおすすめ(レコメンド)機能は、ユーザーの興味関心に基づき、これまでその存在すら知らなかった企業のコンテンツを届けます。
これは、知名度では大企業に及ばない中小・ベンチャー企業にとって、大きなチャンスです。ショート動画を通じて「中の人」の魅力が伝われば、これまでリーチできなかった優秀な潜在層に、自社を知ってもらうきっかけを創出できるのです。
【目的別】採用ショート動画の成功事例5選を徹底分析

ここからは実際の成功事例を、目的別に分析していきましょう。
ここからは、採用ショート動画の成功事例を「認知度向上」「ブランディング」「仕事理解」という3つの目的別に分類し、ご紹介します。
重要なのは、ただ動画を眺めることではありません。各事例について、「企画(なぜウケたか)」「表現(どう見せたか)」「誘導(次の行動)」という独自の分析フレームワークで、成功の裏側にあるロジックを徹底的に解き明かします。ぜひ、「自社ならどう応用できるか?」という視点で読み進めてみてください。
Part 1. 認知度をとにかく高めたい!「バズ」を生んだアイデア事例

バズった事例って、どんな工夫があるんでしょう。
まずは、インパクトのある企画で多くのユーザーの目に留まり、企業の認知度を飛躍的に高めた「バズ事例」を見ていきましょう。
事例1:三和交通(タクシー会社)
出典 三和交通(公式)
事例2:大京警備保障(警備会社)
出典 大京警備保障
Part 2. 会社の魅力を伝えたい!「共感」を呼んだブランディング事例

企業の文化や魅力を伝えるには、社員一人ひとりの内発的動機づけが重要です。
次に、企業独自の文化や働く環境の魅力を伝えることで、「この会社、なんだか良いな」という共感と好意を育むブランディング事例をご紹介します。
事例3:ニトリ(家具・インテリア)
出典 ニトリ新卒採用
事例4:ITベンチャー企業(若手社員インタビュー)
出典 ITベンチャーA社
Part 3. 入社後の理解を深めたい!「こんなはずじゃなかった」を防ぐ仕事紹介事例

リアルな仕事の姿を見せることって、ミスマッチ防止にすごく大事ですよね。
最後に、仕事の良い面だけでなく、大変な面も含めてリアルな姿を伝えることで、入社後のミスマッチを防ぎ、定着率向上に貢献する事例を見ていきましょう。
事例5:建設・製造業(1日密着ドキュメント)
出典 建設・製造業B社
明日から真似できる!予算ゼロからの採用ショート動画「内製化」完全ロードマップ

さあ、ここからが本題です。実際に動画を作るための具体的なステップをお伝えします。
素晴らしい事例の数々を見て、「でも、これを自分たちで作るのは難しそう…」と感じたかもしれません。大丈夫です。ここからは、この記事の核となる、専門知識や高価な機材がなくても、誰でも明日から採用ショート動画を始められる「内製化ロードマップ」を4つのステップでご紹介します。
Step 1.「誰に、何を伝え、どうなってほしいか」たった1枚の企画シートで言語化する

企画って、どうやって考えればいいんでしょうか。

動画制作で最も重要なのは、実は撮影でも編集でもなく企画なんです。
動画制作において、最も重要な工程は「撮影」でも「編集」でもありません。「企画」です。誰に、何を伝えて、見た後にどうなってほしいのか。ここがブレてしまうと、どんなに映像が綺麗でも、誰の心にも響かない動画になってしまいます。
Step 2. 撮影はスマホでOK。ただし「音」と「光」だけは妥協しない

高価な機材は不要ですが、音と光の2点だけは意識してください。
「良い動画のためには、一眼レフカメラが必要ですか?」という質問をよく受けますが、答えは「No」です。今のスマートフォンに搭載されているカメラの性能は、ショート動画を撮影するには十分すぎるほどです。
ただし、最低限こだわってほしいポイントが2つだけあります。それは「音」と「光」です。
Step 3. 無料アプリで十分!カットとテロップ入れの基本ルール

編集も無料アプリでできるんですね。
撮影した映像は、無料の動画編集アプリを使って編集しましょう。「CapCut」や「VLLO」といったアプリは、直感的な操作で、プロ並みの編集が可能です。
初心者がまず覚えるべき編集作業は、下記の3つだけです。
| カット | 不要な部分を切り取って、テンポの良い動画にする。「えーっと」「あのー」といった不要な間(ま)は、ためらわずに全てカットする。少しテンポが速すぎると感じるくらいが、ショート動画では丁度良いです。 |
| テロップ(字幕) | 話している内容を文字で表示する。音声なしで視聴するユーザーも多いため、テロップは必須です。重要なキーワードは色を変えたり、サイズを大きくしたりして、視覚的に強調しましょう。 |
| BGM | 動画の雰囲気に合った音楽を入れる。各アプリやTikTokなどが提供する、商用利用可能な音源の中から選びましょう。動画の雰囲気を決定づける重要な要素ですが、声と被らないよう、音量は控えめに設定するのがポイントです。 |
これだけの作業でも、見違えるほど動画のクオリティは上がります。
Step 4. 投稿して終わりじゃない。最低限見るべき3つの指標と改善アクション

投稿後の振り返りが、次の成功に繋がります。
動画を投稿したら、必ず「振り返り」を行いましょう。SNSの分析機能(インサイト)を使えば、誰でも無料でデータを見ることができます。しかし、全ての数字を追いかける必要はありません。初心者がまず注目すべき指標は、以下の3つです。
- 平均視聴時間(視聴維持率):視聴者が動画を平均で何秒まで見てくれたか、という指標です。もし動画の冒頭(最初の3秒)で多くの人が離脱しているなら、掴みの部分に改善の余地があります。
- エンゲージメント率(いいね・コメント・保存数):視聴者が動画に対して、どれだけ反応してくれたかを示す指標です。コメントが多ければ、視聴者の関心を引く内容だったと言えます。保存数が多ければ、「後で見返したい」と思われる有益な情報だったと判断できます。
- プロフィールへのアクセス数:動画をきっかけに、何人があなたの会社のプロフィールページを訪れたか、という指標です。この数字が多ければ、動画が採用候補者への「興味の入り口」として機能している証拠です。
これらのデータを見て、「次はもっと冒頭のインパクトを強くしてみよう」「今回は質問を投げかけるテロップを入れてみよう」といった仮説を立て、次の動画制作に活かす。このPDCAサイクルを回し続けることが、成功への唯一の道です。
主要プラットフォーム(TikTok/YouTube/Instagram)の使い分け戦略

どのSNSで投稿するのがベストなんでしょうか。
「で、結局うちはどのSNSで動画を投稿すればいいの?」という疑問に答えるため、主要3大プラットフォームの特性と、それぞれに向いている企業を比較表にまとめました。自社の目的やターゲットに合わせて、最適なプラットフォームを選びましょう。
| 評価軸 | TikTok | YouTube Shorts | Instagram Reels |
|---|---|---|---|
| ユーザー層 | 10代〜20代が中心。最近は30代以上も増加。 | 幅広い年齢層。他のYouTube動画からの流入も。 | 20代〜30代の女性が中心。男性も増加傾向。 |
| 拡散力 | 非常に高い。フォロワー数に関係なく、コンテンツの質次第で爆発的に拡散する可能性がある。 | 高い。既存のチャンネル登録者以外にも広く表示される。 | 中程度。フォロワーへのリーチが中心だが、発見タブからの流入も期待できる。 |
| 求められるコンテンツ | エンタメ性、トレンド、面白さ、意外性。 | ハウツー、知識、学び。既存の長尺動画の切り抜きも有効。 | おしゃれ、Vlog、共感、企業の裏側。ブランドの世界観を表現しやすい。 |
| おすすめの企業 | 知名度を問わず、とにかくバズらせて認知度を上げたい企業。柔軟で遊び心のある企画ができる企業。 | 既にYouTubeチャンネルを持っている企業。ハウツーや専門知識を伝えたいBtoB企業。 | デザインや世界観に強みを持つ企業(アパレル、化粧品、食品など)。企業のブランディングを重視したい企業。 |
一つのプラットフォームに絞る必要はありません。まずは自社と最も相性の良さそうなプラットフォームで挑戦し、慣れてきたら、同じ動画を他のプラットフォームにも展開していくのが効率的です。
よくある質問(FAQ)

よくいただく質問にお答えしましょう。
最後に、採用ショート動画を始めるにあたって、担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
まとめ:完璧な動画より、まず1本。あなたの会社の「リアル」を届けよう

100点の完璧な動画を目指すより、まずは60点で良いので最初の1本を世に出すことが大切です。
ここまで、採用ショート動画の重要性から、具体的な成功事例、そして明日から始められる内製化ロードマップまで、網羅的に解説してきました。
たくさんの情報に触れて、「やるべきことが多くて大変そう…」と感じたかもしれません。しかし、最も伝えたいメッセージは、たった一つです。
100点の完璧な動画を目指す必要は、全くありません。
大切なのは、この記事のロードマップを参考にしながら、まずは60点で良いので、あなたの会社の「リアル」が伝わる最初の1本を、世の中に公開してみることです。
社員の飾らない笑顔、少し雑然としているけれど活気のあるオフィス、仕事に対する真摯な想い。そうした「生の情報」こそが、未来の仲間となるかもしれない候補者の心を、何よりも強く動かすのです。

変化を起こすって、まずは気づくことからなんですね。
その小さな一歩が、あなたの会社の採用活動を、そして未来を、大きく変えるきっかけになるはずです。



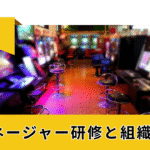
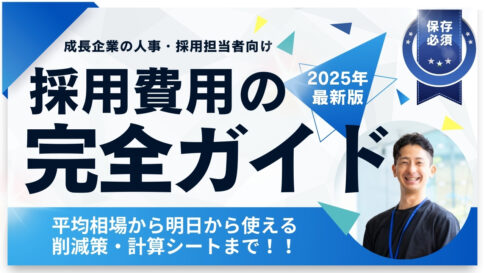

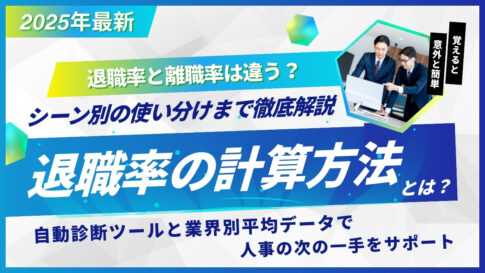

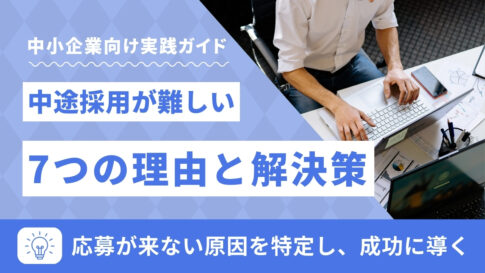
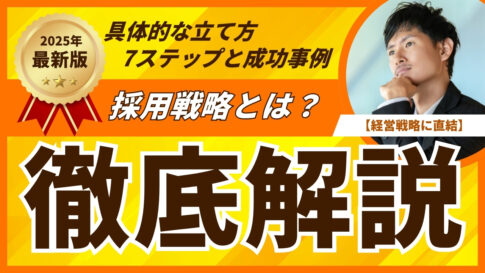
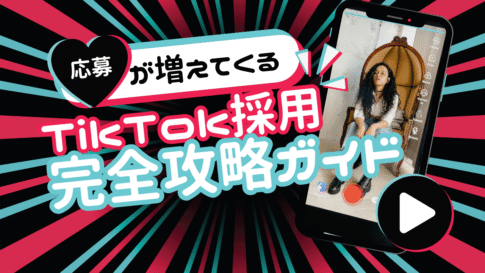




組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。