
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
- 1 【初心者でも大丈夫!】採用動画の作り方で、こんなお悩みありませんか?
- 2 予算ゼロでも『すごいね!』と言われる採用動画の作り方
- 3 【全8STEP】予算ゼロでも大丈夫!採用動画の作り方 完全ロードマップ
- 4 Step 1:企画「誰に、何を伝えるか」を決める
- 5 Step 2:構成「動画の設計図」を作る
- 6 Step 3:絵コンテ「映像のイメージ」を具体化する
- 7 Step 4:撮影準備「スマホと100均グッズ」でOK
- 8 Step 5:撮影「スマホでプロっぽく」撮るコツ
- 9 Step 6:編集「無料ツールCanva」でプロ級の仕上がりに
- 10 Step 7:BGM・ナレーション「動画の雰囲気」を決定づける
- 11 Step 8:公開と活用「作って終わり」にしない
- 12 採用動画の作り方に関するよくある質問(FAQ)
- 13 まとめ:最初の一歩を踏み出して、最高の採用動画を作りましょう!
【初心者でも大丈夫!】採用動画の作り方で、こんなお悩みありませんか?

採用活動に動画が効果的って聞くんですけど、正直何から始めればいいのか全然分からなくて…。
「採用活動に動画が効果的らしい」と聞いてはいるものの、いざ自分が作る立場になると、何から手をつけていいか分からず、頭を抱えてしまうことはありませんか。特に、専門の部署や担当者がいない場合、その悩みはより一層深くなるものです。
もしかして、あなたも今、こんなことで悩んでいませんか?
もし、これらの悩みに一つでも当てはまったなら、どうかご安心ください。この記事は、まさにそんなあなたのためにお届けするものです。
予算ゼロでも『すごいね!』と言われる採用動画の作り方

予算や専門知識がなくても、スマホと無料ツールだけで十分に魅力的な採用動画は作れますよ。
この記事は、単なる採用動画の作り方を解説するだけの記事ではありません。あなたが明日から、いいえ、今日からすぐに具体的な作業を始められるように作られた『実践マニュアル』です。
この記事を最後まで読めば、専門的な知識や高価な機材、そして予算が一切なくても、あなたの会社やチームの魅力が伝わる採用動画を、あなた自身の手で作り上げることができます。そのために必要なのは、いつもあなたが使っている「スマートフォン」と、無料で使えるデザインツール「Canva」だけです。
さあ、私たちと一緒に、採用活動を成功に導く動画制作の第一歩を踏み出しましょう。
すぐに使える!採用動画 構成案テンプレート&インタビュー質問リスト50選

構成を考えるのが一番大変そうで不安です…。
「でも、やっぱり構成を考えるのが一番大変そう…」と感じるかもしれません。ご安心ください。この記事では、プロのノウハウが詰まった「構成案テンプレート」と、インタビューでそのまま使える「質問リスト」をご用意しました。
このテンプレートを使えば、動画制作で最も時間がかかる「考える時間」を大幅に短縮でき、すぐに具体的な制作作業に入ることができます。まずは、こちらからダウンロードして、手元に置きながら記事を読み進めてみてください。
▼▼▼ 今すぐ無料でダウンロード ▼▼▼
採用動画 構成案テンプレート&質問リスト50選(Googleドキュメント)
※ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください。

このテンプレートを手に入れるだけで、動画制作は半分以上終わったようなものです。
【全8STEP】予算ゼロでも大丈夫!採用動画の作り方 完全ロードマップ

それでは、具体的な制作手順を8つのステップに分けて解説していきます。
それでは、具体的な制作手順に入っていきましょう。採用動画の制作は、大きく分けて以下の8つのステップで進めていきます。一つ一つのステップは、決して難しいものではありません。
企画「誰に、何を伝えるか」を決める
構成「動画の設計図」を作る
絵コンテ「映像のイメージ」を具体化する
撮影準備「スマホと100均グッズ」でOK
撮影「スマホでプロっぽく」撮るコツ
編集「無料ツールCanva」でプロ級の仕上がりに
BGM・ナレーション「動画の雰囲気」を決定づける
公開と活用「作って終わり」にしない
このように、企画から公開・活用まで、ステップごとに順番に進めていけば、動画制作が初めての方でも、迷うことなくゴールまでたどり着くことができます。
Step 1:企画「誰に、何を伝えるか」を決める

動画制作で最も重要なのは、実は企画段階なんです。ここをしっかり固めることが成功の鍵ですよ。
動画制作において最も重要な土台となるのが、この「企画」のステップです。どんなに撮影や編集の技術が高くても、企画がしっかりしていなければ、誰の心にも響かない動画になってしまいます。料理で言えば、何を作るか(レシピ)を決める、最も大切な工程です。
ターゲット(ペルソナ)を明確にする

ターゲットを明確にするって、具体的にどこまで絞り込めばいいんでしょうか。
まず最初に、「誰に」その動画を届けたいのかを具体的に設定しましょう。例えば、社会人経験のない新卒学生に届けるのか、あるいは特定のスキルを持った中途採用者に届けたいのかによって、動画で伝えるべきメッセージの内容や表現のトーンは大きく変わってきます。
動画で伝える「コンセプト」を一つに絞る

あれもこれもと欲張ると、結局何も伝わらない動画になってしまいます。一つに絞ることが大切です。
次に、「何を」一番伝えたいのか、動画のコンセプトを一つだけ決めましょう。事業内容の面白さ、風通しの良い企業文化、尊敬できる社員の人柄など、あなたの会社の魅力はたくさんあるはずです。しかし、短い動画の中で多くを伝えようとすると、結局何も伝わらない散漫な印象になってしまいます。「この動画を見終わった人に、これだけは感じてほしい」というメッセージを一つに絞ることが、成功への近道です。
Step 2:構成「動画の設計図」を作る

企画で決めたコンセプトを、実際にどう映像化するか。ここが設計図作りのステップです。
企画で決めたコンセプトを、どのように映像で表現していくか。その設計図となるのが「構成」です。このステップで、動画全体の流れや時間配分、各シーンで伝える内容などを具体的に決めていきます。
テンプレートを使って構成案を埋めてみよう

テンプレートがあれば、ゼロから考えなくていいので安心ですね。
ここで、先ほどダウンロードしていただいた「構成案テンプレート」の出番です。テンプレートには、「オープニング」「事業紹介」「社員インタビュー」「オフィスツアー」「エンディング」といった、採用動画でよく使われる項目があらかじめ用意されています。
この例のように、各項目に「何を」「何秒くらいで」伝えるかを具体的に書き込んでいくだけで、動画の骨格が完成します。
Step 3:絵コンテ「映像のイメージ」を具体化する

絵コンテって、絵が上手じゃないとダメなんですよね…。
構成案で決めた動画の流れを、さらに具体的な映像のイメージに落とし込むのが「絵コンテ」です。絵コンテを作る一番の目的は、撮影者や出演者など、制作に関わる全員が「どんな映像を撮るのか」という完成イメージを共有することにあります。

絵を描くのが苦手でも全く問題ありません。簡単な図とメモで十分なんです。
「絵を描くのが苦手だから無理…」と思う必要は全くありません。上手な絵は一切不要です。PowerPointや手書きで、「誰が」「どこで」「何をしている」かが分かる簡単な図と、セリフやナレーションを書き込むだけで十分です。この一手間が、後の撮影や編集を驚くほどスムーズにしてくれます。
Step 4:撮影準備「スマホと100均グッズ」でOK

いよいよ撮影です。専用機材がなくても、十分にプロ並みの映像が撮れますよ。
いよいよ撮影です。「専用のカメラや機材がないと…」と心配になるかもしれませんが、心配は無用です。最近のスマートフォンと、少しの工夫さえあれば、プロ顔負けの映像を撮ることが可能です。
必要な機材は「スマートフォン」だけ
まず、主役となる撮影機材は、あなたが普段使っているスマートフォンです。最近のスマートフォンのカメラ性能は非常に高く、解像度を「4K」や「1080p/60fps」に設定すれば、Webで公開するには十分すぎるほど高画質な映像が撮影できます。撮影前には、カメラのレンズの汚れを綺麗に拭き取ることを忘れないようにしましょう。
あると便利な撮影グッズ(100円ショップで揃います)

100円ショップでも揃えられるなら、気軽に試せますね。
スマートフォンの他に、もし準備できるなら、以下のグッズがあると動画のクオリティが格段にアップします。驚くことに、これらの多くは100円ショップで手に入れることができます。
これらのちょっとした工夫が、動画の「素人っぽさ」をなくすための大きなポイントになります。
Step 5:撮影「スマホでプロっぽく」撮るコツ

機材が揃ったら、いよいよ撮影本番です。少し意識するだけで映像が見違えますよ。
機材が準備できたら、いよいよ撮影本番です。ここでは、少し意識するだけで映像が見違える、スマートフォン撮影の基本的なコツをご紹介します。
撮影前に確認すべき3つの基本設定
撮影を始める前に、必ず確認しておきたい基本的な設定が3つあります。これらは簡単なことですが、忘れがちなので注意しましょう。
- レンズのクリーニング: 指紋やホコリが付いていると、映像がぼやける原因になります。メガネ拭きなどの柔らかい布で優しく拭きましょう。
- グリッド線の表示: カメラ設定でグリッド線を表示させると、水平・垂直がとりやすくなり、安定した構図で撮影できます。
- 十分なバッテリーと空き容量: 撮影途中でバッテリーが切れたり、容量不足になったりすると大変です。事前にフル充電し、不要なデータは整理しておきましょう。
これらの準備が、スムーズな撮影を支えてくれます。
絶対に避けたい「手ブレ」と「暗さ」対策

手ブレと暗さ、これが一番の失敗要因なんですね。
動画のクオリティを大きく下げてしまう二大要因が「手ブレ」と「暗さ」です。これを防ぐだけでも、一気にプロっぽい映像に近づきます。
手ブレ対策には、前述の三脚を使うのが最も効果的です。もし三脚がない場合は、壁に寄りかかったり、脇を締めたりして、できるだけ体を固定して撮影しましょう。また、映像の明るさを確保するためには、照明機材は必要ありません。日中の自然光が入る窓際で撮影するだけで、被写体の表情は驚くほど明るく自然になります。
インタビュー動画を魅力的に撮る方法

インタビューは目線と背景の工夫で、印象が大きく変わります。
インタビュー動画を撮影する際は、話し手の目線が重要です。カメラのレンズを直接見てもらうのではなく、カメラの少し横にいるインタビュアー(聞き手)の方を向いて話してもらうと、より自然な雰囲気になります。また、背景に会社のロゴや観葉植物などを少し映り込ませることで、映像の情報量が増え、より魅力的な画面になります。
Step 6:編集「無料ツールCanva」でプロ級の仕上がりに

撮影した素材を一つの作品に仕上げるのが編集です。無料のCanvaで十分なクオリティが実現できます。
撮影した映像素材を繋ぎ合わせ、一つの動画作品に仕上げていくのが「編集」の工程です。専門の動画編集ソフトは高価で操作も難しいものが多いですが、無料のデザインツール「Canva」を使えば、初心者でも直感的な操作でプロ級の動画編集が可能です。
Canvaとは?なぜおすすめなの?

Canvaって、本当に無料で使えるんですか。
Canvaは、本来はプレゼン資料やSNS投稿用の画像をデザインするツールですが、動画編集機能も非常に優れています。
これらの理由から、動画編集が初めての方に最もおすすめできるツールです。
【画面キャプチャで解説】Canvaでの基本編集フロー

ここからは、Canvaを使った具体的な編集手順を解説していきます。
ここからは、Canvaを使った具体的な編集手順を、画面のイメージと共に解説していきます。アカウント登録(無料)を済ませて、一緒に操作してみてください。
1. 素材(動画・画像)の取り込み
まず、Canvaのトップページから「動画」プロジェクトを作成します。次に、左側のメニューにある「アップロード」から、撮影した動画や使いたいロゴ画像などの素材をすべてアップロードしましょう。アップロードした素材は、下のタイムラインにドラッグ&ドロップするだけで配置できます。
2. 不要な部分のカット・並び替え
タイムラインに配置した動画クリップは、両端をドラッグすることで簡単に長さを調整(トリミング)できます。また、クリップの順番を入れ替えたい場合は、ドラッグ&ドロップで好きな位置に移動させるだけです。インタビューの「えーっと…」といった不要な部分をカットしていくだけで、テンポの良い動画になります。
3. 読ませるテロップ(字幕)の入れ方
左側メニューの「テキスト」から、好きなデザインの見出しを追加します。フォントの種類や色、大きさは自由に変更可能です。特にインタビュー動画では、話している内容をすべてテロップで表示させると、音声が出せない環境でも内容が伝わるため、視聴者に非常に親切です。
4. 印象を決定づけるBGMの追加
動画の雰囲気を大きく左右するのがBGMです。Canvaには、無料で使えるおしゃれなBGM音源が多数用意されています。左側メニューの「オーディオ」から、動画のコンセプトに合った曲を選んでタイムラインに追加しましょう。音量の調整もスライダーで簡単に行えます。
Step 7:BGM・ナレーション「動画の雰囲気」を決定づける

BGMは動画の印象を決める重要な要素です。慎重に選びましょう。
Canvaにも豊富なBGMがありますが、より多くの選択肢から選びたい場合は、著作権フリーの音源を配布している専門サイトを利用するのもおすすめです。
また、もし動画にナレーションを入れたい場合は、スマートフォンのボイスメモ機能で録音した音声を取り込むだけでも十分な品質になります。静かな環境で、ゆっくりはっきりと話すことを心がけましょう。
Step 8:公開と活用「作って終わり」にしない

せっかく作った動画、しっかり活用していきたいですね。
素晴らしい動画が完成したら、いよいよ公開です。まずはYouTubeにアップロードするのが一般的です。タイトルには「【株式会社〇〇】2025年度 新卒採用メッセージ」のように、会社名と動画の内容がわかるキーワードを入れましょう。
そして最も重要なのは、「作って終わり」にしないことです。完成した動画は、自社の採用サイトやSNS(X, Instagram, Facebookなど)で積極的に発信し、一人でも多くの求職者に届けましょう。動画は、一度作れば様々な場面で活用できる、非常に強力な資産となります。

動画は一度作れば、様々な採用シーンで活用できる強力な資産になります。
採用動画の作り方に関するよくある質問(FAQ)

最後に、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でお答えします。
最後に、採用動画の作り方に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でお答えします。
Q1. 採用動画の適切な長さは?

動画の長さって、どれくらいがベストなんでしょうか。
動画の適切な長さは、公開する媒体や目的によって異なります。以下を目安にしてみてください。
| 媒体・目的 | 推奨される長さ | ポイント |
| SNS広告・TikTok | 15秒〜1分 | 冒頭で惹きつけ、最後まで見てもらう工夫が必要。 |
| 採用サイト・YouTube | 2分〜5分 | 企業理念や事業内容など、少し深い内容を伝えるのに適している。 |
| 会社説明会・イベント | 5分〜10分 | 複数の社員インタビューを盛り込むなど、じっくり見せる構成が可能。 |

まずは2〜3分程度の動画を一本作り、それを短く編集してSNS用に活用するのがおすすめです。
Q2. 内製する場合の費用は結局いくらかかる?

予算ゼロって言っても、実際にはどれくらいかかるんですか。
内製する場合の費用は、どこまでこだわるかによって大きく変わりますが、やり方次第では完全に0円で制作することも可能です。
| プラン名 | 費用目安 | 内容 |
| 完全0円プラン | ¥0 | 機材: スマートフォン 編集: Canva無料版 BGM: Canva無料音源 |
| クオリティUPプラン | 約 ¥3,000〜¥10,000 | 機材: スマホ用三脚・マイクを追加 編集: Canva無料版 BGM: 無料音源サイト |
| こだわりプラン | 約 ¥30,000〜 | 機材: エントリーモデルのカメラ 編集: Canva Pro版 (有料) BGM: 有料音源サイト |

まずは完全0円プランで一度作ってみて、必要に応じて機材を追加投資していくのが良いでしょう。
Q3. やはりプロ(制作会社)に頼んだ方がいい?

やっぱり内製だと限界があるのかな…。
内製と外注(制作会社への依頼)には、それぞれメリット・デメリットがあります。
| 内製 | 外注(制作会社) | |
|---|---|---|
| メリット | ・費用を抑えられる ・修正や変更が柔軟 ・リアルな雰囲気が伝わる | ・圧倒的に高品質 ・企画から丸投げできる ・自社の工数がかからない |
| デメリット | ・クオリティの担保が難しい ・制作に時間がかかる ・ノウハウの学習が必要 | ・費用が高い(50万円〜) ・制作期間が長い ・修正に費用がかかる場合も |

採用ブランドイメージを特に重視する場合は外注も検討価値がありますが、まずは内製にチャレンジしてみることをおすすめします。
まとめ:最初の一歩を踏み出して、最高の採用動画を作りましょう!

完璧な動画を目指す必要はありません。あなたの会社の魅力を、誠実に伝えることが大切です。
今回は、予算や専門知識がなくても、スマートフォンと無料ツールCanvaだけで採用動画を内製する方法を、8つのステップで詳しく解説しました。
この記事をここまで読んでくださったあなたは、もう採用動画の作り方に関する十分な知識を持っています。完璧な動画を目指す必要はありません。大切なのは、あなたの会社の魅力を、あなたの言葉と映像で、誠実に伝えることです。

私も早速テンプレートを開いて、企画から始めてみます。
まずはこの記事で提供したテンプレートを開いて、企画の第一歩を踏み出してみませんか。その小さな一歩が、未来の素晴らしい仲間と出会うための、大きなきっかけになるはずです。


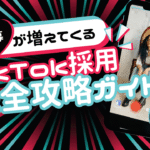


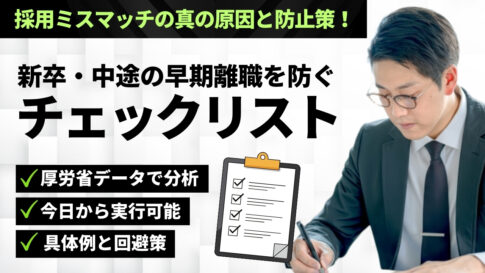
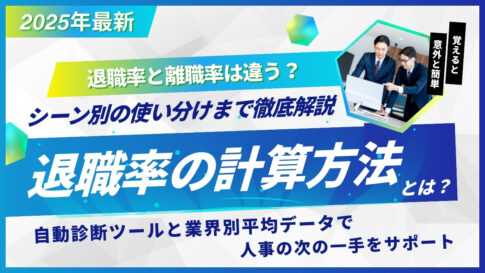
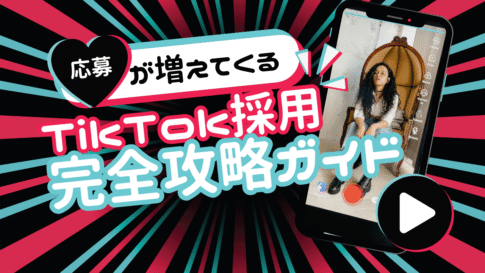

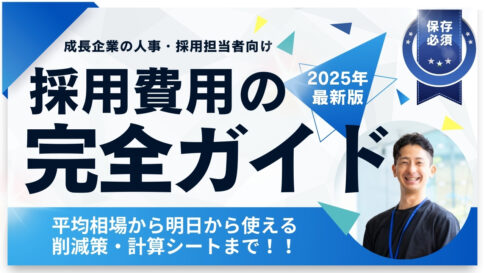





組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。