
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
採用コンテンツ、何から始める?担当者が抱える共通の悩み

採用コンテンツって重要だとはわかっているんですけど、何から手をつければいいか正直迷ってしまいます。

多くの採用担当者が同じ悩みを抱えています。重要性は理解していても、具体的な第一歩が見えないんですよね。
「採用活動において、コンテンツは重要だ」。上司や同僚、そして多くのWeb記事がそう語りかけます。
しかし、いざ自社の採用担当として「コンテンツを強化しろ」というミッションを与えられたとき、何から手をつければ良いのか、途方に暮れてしまうことはないでしょうか。多くの採用担当者が、あなたと同じように「重要性はわかるが、具体的な一歩が踏み出せない」という課題を抱えています。
競合他社の洗練された採用サイトを眺めては、「うちもこんなお洒落な社員インタビューを載せるべきだろうか?」と焦りを感じたり、とりあえず企画書を書いてみたものの、「なぜ数ある施策の中で、今これを行う必要があるのか?」という上司の問いに、自信を持って答えることができなかったり。
そんな経験は、決してあなただけのものではありません。
よくあるコンテンツリストの罠|情報の羅列だけでは課題は解決しない

ネットで調べると「採用コンテンツ〇〇選」みたいな記事はたくさん出てくるんですけど、読んでも結局うちは何をすべきかわからなくて。

情報の羅列だけでは、自社固有の課題に対する最適解は見つかりません。「What」ではなく「How」が重要なんです。
この課題を解決しようとWebで検索すると、「採用サイトのコンテンツ12選」といった網羅的な記事が数多く見つかります。それらの記事は一見すると非常に有益に思えますが、読み終えた後に「で、結局うちは何から始めるべきなんだろう?」という、新たな疑問が生まれることも少なくありません。
情報の羅列だけでは、自社の固有の課題や採用ターゲットに合わせた「最適な一手」を見つけ出すことは困難です。
これは豊富な食材リストを渡されても、作りたい料理が決まっていなければキッチンで立ち尽くしてしまうのと同じです。多くの記事は「What(何があるか)」は教えてくれますが、最も重要な「How(どう選び、どう活かすか)」に応えてくれないのです。
最も重要なのは戦略的な「選択軸」と「実行プラン」

採用担当者に必要なのは、戦略的な選択軸と具体的な実行プランです。
この記事は、単なるコンテンツのリストアップに終始しません。採用担当者であるあなたが、自信を持って次の一歩を踏み出すための「戦略的な選択軸」と「具体的な実行プラン」を提供することを目的としています。
この記事を最後まで読むことで、あなたは以下のものを手に入れることができます。
もう情報の波に溺れるのはやめにしましょう。自社の採用活動を成功に導くための、確かな羅針盤を手に入れてください。
前提として採用市場は変化している│候補者は「情報収集のプロ」

最近の求職者の方って、本当にいろんなチャネルで情報収集されてますよね。

その通りです。候補者の情報収集行動は大きく進化しています。企業側も変化に対応する必要があります。
現代の採用市場における最も大きな変化は、候補者の情報収集行動の進化です。
かつて候補者が企業の情報を得る手段は、公式の採用サイトや求人広告が中心でした。しかし今は、SNS、社員の個人ブログ、企業の口コミサイト、ニュース記事など、あらゆるチャネルを駆使して、企業の「リアルな姿」を徹底的にリサーチします。
実際に、ある調査によれば、転職活動者の約8割が、企業の採用サイトだけでなく、SNSや口コミサイトを必ず確認すると回答しています。
これは、企業側からの一方的なメッセージだけでは、候補者の心を動かすことが難しくなっていることを意味します。候補者は、自分たちが本当に知りたい情報、つまり「実際に働く人々の声」や「企業のカルチャー」「社内の雰囲気」といった情報を、コンテンツを通じて探し求めているのです。
コンテンツが採用ブランディングと候補者体験の質を決める

採用コンテンツは、もはや単なる情報提供のツールではありません。採用ブランディングそのものなんです。
採用コンテンツは、もはや単なる情報提供のツールではありません。それは、候補者とのあらゆる接点において「この会社で働くとは、どういうことか」を伝える、採用ブランディングそのものです。
候補者が最初に目にするブログ記事から、選考過程で送られてくるメールの文面、そして内定者向けのコンテンツまで、その一つひとつが候補者体験(Candidate Experience)を形作ります。
優れた採用コンテンツは、候補者にポジティブな企業イメージを与え、入社意欲を高めるだけでなく、入社後のミスマッチを防ぎ、定着率の向上にも貢献します。
戦略的に設計されたコンテンツは、採用活動全体の質を向上させる、強力なエンジンとなるのです。
【戦略編】自社に最適な採用コンテンツポートフォリオの設計方法

いよいよ具体的な設計方法ですね。しっかり学ばせていただきます。
Step1. 誰に届けたいのか?採用ペルソナを明確に定義する

優れたコンテンツ戦略は、常に「誰に届けたいのか」という問いから始まります。
優れたコンテンツ戦略の出発点は、常に「誰に届けたいのか?」という問いから始まります。ターゲットとなる理想の候補者像、すなわち「採用ペルソナ」を明確に定義することが、心に響くコンテンツを生み出すための第一歩です。
ペルソナを設計する際は、スキルや経験といった定量的な情報だけでなく、その人物が「仕事に何を求めているのか」「どのような価値観を大切にしているのか」「キャリアにおいてどんな不安や希望を抱いているのか」といった、定性的な内面にまで踏み込んで解像度を上げることが重要です。
明確なペルソナが存在することで、発信するメッセージやコンテンツのトーン&マナーがブレなくなり、候補者の心に「これは自分のためのメッセージだ」と感じさせることができます。
Step2. 候補者の心を動かす採用ファネルの各段階で「知りたいこと」をマッピングする

採用ファネルって、マーケティングでよく聞く考え方ですよね。

その通り。候補者の心理プロセスを可視化することで、各段階に最適なコンテンツが見えてきます。
採用ペルソナを定義したら、次はそのペルソナが自社を認知し、応募、そして入社に至るまでの心理的なプロセスを可視化します。このプロセスは、一般的に「採用ファネル」と呼ばれ、コンテンツ戦略を立てる上で非常に有効なフレームワークです。
| 採用ファネル | 候補者の心理状態 | 候補者が知りたいこと(コンテンツの役割) |
| 認知 | 「こんな会社があったんだ」 | まずは社名や事業内容を知ってもらう。業界内でのユニークな取り組みやビジョンを伝える。 |
| 興味・関心 | 「なんだか面白そうな会社だな」 | どんな人たちが、どんな想いで働いているのかを知りたくなる。具体的な仕事内容や社風に興味を持つ。 |
| 比較・検討 | 「他社と比べて、どう違うんだろう?」 | 待遇や福利厚生だけでなく、独自のキャリアパスや成長環境、カルチャーフィットするかを真剣に吟味する。 |
| 応募・選考 | 「この会社で働きたい」 | 自分のスキルや経験がどう活かせるか、入社後の具体的なイメージを掴みたい。選考プロセスへの不安を解消したい。 |
このように、候補者の心理フェーズに合わせて、適切なコンテンツを戦略的に配置することが、採用成功の鍵となります。
Step3. 企業の成長フェーズで考えるコンテンツの優先順位

企業の成長フェーズによって、優先すべきコンテンツは異なってきます。
設立間もないスタートアップや、事業が急成長しているフェーズの企業では、まだ世間的な知名度や盤石な福利厚生で勝負することは難しいかもしれません。
だからこそ、コンテンツで伝えるべきは、待遇(What)や制度(How)以上に、「なぜこの事業をやるのか(Why)」という熱い想いやビジョンです。
創業者のストーリー、解決したい社会課題、そしてそのビジョンに共感して集まった魅力的な「人」にフォーカスしたコンテンツは、企業のカルチャーを伝え、未来のコアメンバーとなる人材を惹きつける強力な磁石となります。
また、すでに事業基盤が安定し、多くの従業員が在籍する成熟期の企業では、その多様性自体が魅力となります。
画一的なメッセージではなく、多様なキャリアパス、充実した研修制度、ユニークな福利厚生、様々な部署のリアルな仕事内容など、「ここで働く魅力」を多角的に伝えるコンテンツが有効です。
候補者一人ひとりが「自分に合った働き方ができそうだ」「この環境なら成長できそうだ」と感じられるよう、具体的で豊富な情報を提供することで、より幅広い層の優秀な人材にアプローチすることが可能になります。
【実践編】採用ファネル別・コンテンツの種類と成功事例

具体的にどんなコンテンツを作ればいいのか、すごく知りたいです。
[認知] まずは知ってもらうためのコンテンツ

まずは知ってもらうことが全ての始まりです。認知段階のコンテンツから見ていきましょう。
まず知ってもらうためにはどのようなコンテンツが必要か、要件を整理し、具体的な媒体・チャネルを知っていきましょう。
採用ブログ・オウンドメディア
採用ブログやオウンドメディアは、自社の魅力を継続的に発信し、潜在的な候補者との最初の接点を作るための拠点です。
業界のトレンド解説や、自社の技術的な取り組み、企業文化に関する記事などを通じて、「この分野に強い会社」「面白そうな取り組みをしている会社」として認知を広げることが目的です。
SNS(X, Instagram, etc.)での発信
SNSは、よりリアルタイムでカジュアルな情報発信を通じて、企業の「素顔」を見せるのに最適なツールです。
特にX(旧Twitter)やInstagramは、日常のオフィス風景、社内イベントの様子、社員のちょっとしたつぶやきなどを通じて、候補者が親近感を抱きやすいプラットフォームです。
成功のコツは、完璧な広報コンテンツを目指すのではなく、少し肩の力を抜いて、社員の個性や会社のカルチャーが自然に伝わるような投稿を心がけることです。これにより、候補者は企業をより「身近な存在」として感じることができます。
[興味・関心] もっと知りたいと思わせるコンテンツ

認知から一歩進んで、もっと深く知りたいと思わせる工夫が必要なんですね。
認知の次は、より自社への興味・関心を惹くことが重要です。知ってもらうだけでは応募の動機につながりません。
社員インタビュー・座談会
社員インタビューや座談会は、候補者が「この人たちと一緒に働きたい」と思えるかどうかを判断するための、最も重要なコンテンツの一つです。
仕事のやりがいや大変さ、入社の決め手、今後の目標などを、社員自身の言葉で語ってもらうことで、仕事内容への理解を深めると同時に、企業のカルチャーを伝えます。
よくある失敗は、当たり障りのない「良い話」だけで終始してしまうこと。ある企業では、あえて「入社後に感じたギャップ」や「仕事で経験した最大の失敗」といったテーマにも踏み込むことで、誠実な姿勢を示し、候補者からの信頼を獲得しています。
成功のポイントは、候補者が本当に聞きたいであろう質問を投げかけ、社員の「本音」を引き出すことです。
1日の仕事の流れ(Vlog風コンテンツ)
「入社後、自分がどんな毎日を送ることになるのか」は、候補者にとって最大の関心事の一つです。
ある特定の職種の社員に密着し、出社から退社までの一日の流れを時系列で紹介するコンテンツは、この疑問に具体的に答えることができます。
特に最近では、テキストと写真だけでなく、短い動画を組み合わせたVlog(ビデオブログ)風のコンテンツが人気です。オフィスの雰囲気や、チームメンバーとのコミュニケーションの様子を映像で見せることで、候補者は自分がその場で働いている姿をよりリアルに想像することができます。
[比較・検討] 他社ではなく「この会社だ」と確信させるコンテンツ

比較検討段階では、候補者に最後の一押しを提供する必要があります。
この会社だと確信させるためには、応募者が自分が働いてる姿をリアルに想像できる必要があります。
部署・プロジェクト紹介
候補者が配属される可能性のある部署や、現在進行中の具体的なプロジェクトについて深く掘り下げるコンテンツは、入社の意思決定を強力に後押しします。
部署のミッション、チームの構成、使用しているツール、現在の課題などを具体的に示すことで、候補者は自身のスキルや経験がどう活かせるかを判断しやすくなります。
「私たちの部署では、現在〇〇という課題解決に取り組んでおり、あなたの△△というご経験は、まさにこの部分で活かせると考えています」といったメッセージは、候補者にとって何よりの口説き文句となるでしょう。
福利厚生・キャリアパス・研修制度の具体的な紹介
給与や待遇はもちろん重要ですが、それと同じくらい、自身の成長につながる環境が整っているかは、優秀な人材ほど重視するポイントです。
キャリアパスのモデルケースを複数提示したり、独自の研修制度や資格取得支援制度について詳しく紹介したりすることで、「この会社は社員の成長に投資してくれる」という強いメッセージになります。
単に制度を羅列するだけでなく、実際にその制度を利用してキャリアアップした社員の声を紹介するなど、具体例を交えることで、情報の説得力は格段に高まります。
失敗談・カルチャーフィットに関する赤裸々な情報
企業のポジティブな側面だけでなく、あえて「過去の失敗談」や「自社が抱える課題」、「こういうタイプの人はうちには合わないかもしれない」といった情報をオープンにすることも、候補者との信頼関係を築く上で非常に有効です。
完璧な企業など存在しません。自社の弱みや課題を誠実に開示する姿勢は、候補者に「正直な会社だ」という印象を与え、長期的な視点でカルチャーフィットする人材の採用に繋がります。
これは、入社後のミスマッチを防ぐための、最も効果的なコンテンツの一つと言えるでしょう。
【効果測定・改善編】採用コンテンツのROIを最大化する思考法

作りっぱなしじゃダメですよね。ちゃんと効果を測定して改善していかないと。

その通りです。効果測定とデータに基づく改善こそが、採用活動のROIを最大化する鍵なんです。
素晴らしい採用コンテンツを制作することは重要ですが、それはゴールではありません。コンテンツは公開してからが本当のスタートです。
「作りっぱなし」で放置してしまうと、そのコンテンツが本当に採用成果に貢献しているのか、どこに改善の余地があるのかが全く分かりません。
効果測定を行い、データに基づいてコンテンツを改善していくサイクルを回すことは、採用活動のROI(投資対効果)を最大化するために不可欠です。
また、具体的なデータは、次なるコンテンツ制作の予算を獲得する際に、上司や経営層を説得するための強力な武器にもなります。
何を測るべきか?採用コンテンツの重要KPI設定例

具体的にどんな指標を見ればいいんでしょうか。
何を測定すれば良いかは、コンテンツの目的によって異なりますが、以下に代表的なKPI(重要業績評価指標)の例を挙げます。
最初から全てを計測するのは難しいかもしれませんが、まずは計測しやすい指標から始め、徐々に範囲を広げていくと良いでしょう。
明日からできる、小さな改善サイクル(PDCA)の回し方

完璧な分析を目指すよりも、小さなPDCAサイクルを回し続けることが大切です。
効果測定と聞くと難しく感じるかもしれませんが、大掛かりな分析ツールがなくても始められることはたくさんあります。
例えば、Google Analyticsを使えば、どのブログ記事がよく読まれているかを無料で分析できます。また、面接の場で候補者に「どのコンテンツが印象に残りましたか?」と直接聞いてみるだけでも、貴重なフィードバックが得られます。
重要なのは、完璧な分析を目指すことではなく、「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」という小さなPDCAサイクルを回し続けることです。
一つの記事のタイトルを少し変えてみる、CTAボタンの文言を工夫してみる。そんな小さな改善の積み重ねが、最終的に大きな採用成果へと繋がっていきます。
まとめ:明日から始める、戦略的採用コンテンツの第一歩

たくさん学べました。まずは小さな一歩から始めてみます。

その姿勢が大切です。戦略的な視点を持って、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
本記事では、単なるコンテンツ事例の紹介に留まらず、自社の採用課題を解決するための「戦略的な考え方」から、制作後の「効果測定と改善」までを網羅的に解説してきました。
重要なポイントは、コンテンツの種類を増やすこと自体が目的ではない、ということです。
本当に大切なのは、届けたい相手に、届けるべきメッセージを、最適な形で提供するという戦略的な視点を持つこと、そして、一度作って終わりではなく、データに基づいて改善を続けることです。
この記事を読んで、やるべきことの多さに圧倒されてしまったかもしれません。しかし、全てを一度に始める必要はありません。まずは、明日からできる小さな一歩を踏み出してみましょう。
この小さな一歩が、貴社の採用活動を成功へと導く、大きな変化の始まりとなるはずです。この記事が、そのための確かな羅針盤となることを心から願っています。


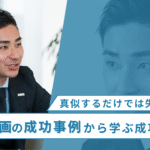
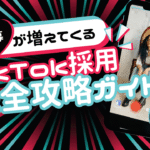

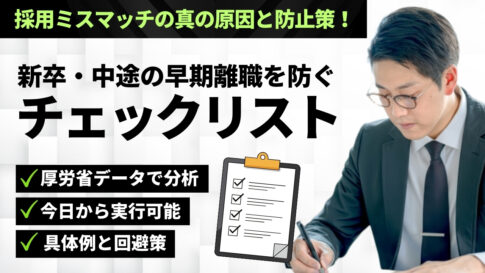



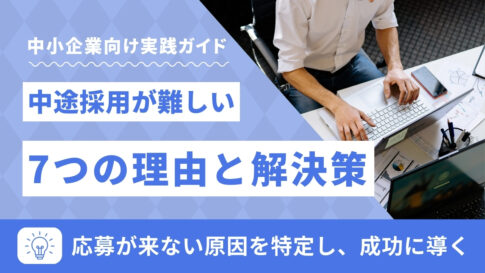
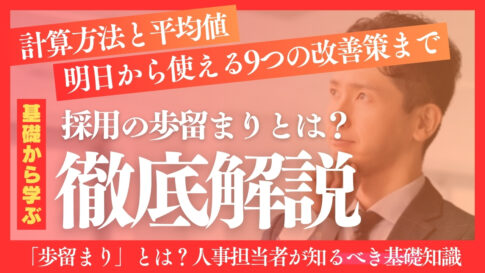
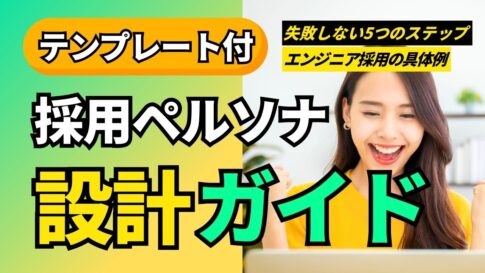



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。